 |
 |
本書は副題にあるように、自分の「弱さ」に悩む若者への指南書である。かつて著者も同じ苦しみを抱き続けていたゆえに、その表現はやさしくて丁寧な励ましに満ちている。「弱さ」に悩む若者たちへの渾身のメッセージと受けとりたい。
著者は「いい子」として少年期を送り、東大に合格はしたが法学部と哲学科を行き来して計12年の大学生活を送り、50歳になってやっと親と訣別できたという哲学者。子供時代より、運動場に出て遊ばなければいけない「休み時間」と「体育」の授業がきらいで、「勉強」や「宿題」が大好きだった。だから、ふつうにしていることで周囲から「いい子」と思われ続けていたが、内心では、長期にわたって自殺の誘惑と隣り合わせの生活をしていたのだという。
本書は、同じ悩みを持つT君すなわち30年前の自分への手紙でつづられる。「どんなことがあっても自殺してはいけない」と説きはじめながら、「親を捨てる」「なるべくひとの期待にそむく」「怒る技術を体得する」「ひとに『迷惑をかける』訓練をする」「自己中心主義を磨きあげる」「幸福を求めることを断念する」「自分はいつも『正しくない』ことを自覚する」「まもなくきみは広大な宇宙のただ中で死ぬ」と諭す。そして、それがそのまま本書の目次となっている。
「傷つきやすいマイノリティである自分たちは、人を傷つけることから実践しよう」というのが面白い。まず、その手始めは自分を苦しませた親を攻撃することから始めようと呼びかける。やさしすぎる「いい子」は、親の願望を自分の願望としてとらえており、しかもそのことに本人も気付いていない。
親とは「バカな生き物」だから「温かい期待の縄でしばり続け、ぼくの全身から血を抜きとるように抵抗力を抜きとり、じわじわとぼくを殺しつづけていることに気がつかないのだった」と語る。また、周囲の人に対しては「わざと約束の時間に遅れ、金を返さず、『酒のせい』にして皆の悪口を言え」と提言する。無言の強制で習性になった「いい子」の殻を破っていこうというのである。
なお、カインとは、世間に対して疑問を発することからぬけられず、孤独を背負って生きねばならない者たちを、神から選ばれた旧約聖書のカインになぞらえているのだ。そして、世俗に溶け込む努力を放棄して、ジコチュウで生き抜けという。
少し気がかりな点もある。みずからをナイーブなマイノリティとし、善意を自称する多くの人たちを鈍感なマジョリティと区分してしまうことや、東大卒で私大教授におさまっていて何が弱者だという反感もあるだろう。若い読者に説教を垂れているけれど、著者のたどり着いた境地は他人を信じないということではなかったのかと、少し意地悪を言ってみたい気もする。
しかし、私にも著者の生育歴と類似した点が思い当たり、これらの悩みにも、また乗り越えるための忠言にも実によく共感できるのだ。著者はその悩みの解決をカント哲学に求め、人生取るに足らずと認めた上でその意味を考え悩むことに人生の価値を見出した。それも納得できる。ただ、著者の思想には、政治、社会、歴史がでてこない。それらも取るに足らないものというのであろうが、私は違っていた。
著者と違って私は、その悩みをマルクス主義で克服したように思う。その分、悩みは20歳代で終了させて著者よりも楽天的な人生が歩めたようだけれど、実はやはり親との訣別は50歳まで持ち越してしまった。しかも決定的な断絶に至る結果を残して・・。それも仕方がなかったのかと著者のメッセージを味わいつつ思う。 |
|
 |
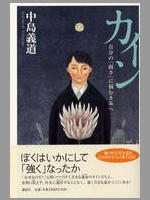 |
 |
『カイン 自分の「弱さ」に悩むきみへ』
中島義道著
講談社
本体価格1500円
発行2002年1月
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|