 |
 |
本書は、痴呆病棟を舞台にして患者・家族と職員がおりなす日常を描いた小説である。著者は精神科医。病棟でのリアルな療養生活の描写とともに、生死の操作、広い意味での科学技術の進歩を問い直す深い意味を込めた著作である。
はじめの数章では、何人かの患者に自分の病状と家庭背景、これまでの生活歴を語らせている。そこで、それぞれの人にとってたった一度の貴重な人生が垣間見られる。ボケによるとみられる思い違いや勘繰りもあったりするが、話がそれなりに理のとおったものであることが、患者に寄り添う筆者の姿勢をあらわしている。
半ばからは、主人公である看護婦の手記の形をとり、職員たちも登場して患者と繰り広げる群像ドラマが生き生きと描かれる。まず最初は、ある朝、女性患者の枕頭台の引き出しに多量の尿が入っていたという騒動からはじまる。それは隣室のオムツのはずれた男性患者が、排泄場所を考えあぐねての仕業だったのだが・・。
ホールには、テレビの相撲を見ながら勝負のつくたびにオーッという声をだして手をたたく人、五百円玉を飲み込んで回盲部にちゃんと納めている人、お地蔵さんのそれぞれの顔を思い浮かべながらひとつずつ丁寧に前掛けを編んでいる人、その仕事が邪魔されないように徘徊患者からガードすることを自分の役割と心得ている人、自分が結婚前の23歳と思い込んでそれになりきっている人など様々の人がいる。
そうした病棟のなかでつぎつぎと起こる障害をもつ人たちの急変と死、それは治療法のない自然死だったのか? 小説は少しサスペンス風の内容をもちはじめる。そして、最終章は看護婦の手紙で締めくくられる。
安楽死が法的に認められた国であるオランダについては、本書でもふれている。その対象には、重篤な障害をもった新生児、長期の昏睡患者、そして重篤な痴呆患者も含まれていて、これらは患者からの要請がなくても医師の判断で行なってよいことになっているのだ。こうした傾向は、今後世界的に広まっていくのではないか。というのは、すでに現在「人の命はすべて平等である」という命題はくずされてきているからである。そのことは、一つの命を助けるといって、死の近い人から一時も早く臓器をとりだそうという脳死・臓器移植にからむ論議を見るだけでもわかる。
個人の人権を尊重することからはじまったはずの「安楽死」が周囲の人の判断でも許されるとなると、ナチスの「安楽死」との違いは何だろう。私たちは人権を意識できない人の人権についてどう考えればいいのだろう。
医師でもある私は、ダブル・スタンダード(二重基準)という言葉について考える。自分は安楽死を希望する。しかし、他人に安楽死(日本ではこの場合もちろん消極的安楽死)を許可することには慎重である。この矛盾をはらんだダブル・スタンダードは、自分一人の行動規準としては明解である。だが、こうしたダブル・スタンダードに依拠しているということは、最終的な解答ではないのだということを認識しておかなければならないだろう。今後もずっと考えつづけるべき難しい命題なのだろうと思う。
|
|
 |
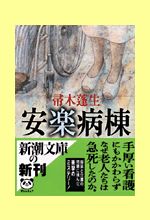 |
 |
『安楽病棟』
帚木蓬生著
新潮文庫
本体価格819円
発行2001年
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|