 |
 |
�@�u���ɂȂ�Ȃ������v�Ƃ́A���͂ɐK����U�鑖��ɂȂ邱�Ƃ��A�K���������ē����镉�����ɂȂ邱�Ƃ����ۂ����Ƃ����Ӗ��ł���B�����A���҂�36�N�Ԃɂ킽��ٔ����Ƃ��Ă̐����ɂ����āA��т��Ă݂�����̗ǐS��ۂ��Â����B
�@���̊Ԃ����������Ȏ����̈���a�̎R�̖����ȍقł̌˕ʖK�⎖���ł������B�˕ʖK��֎~�͌��E�I���@138���P���ŋK�肳��Ă���A���̈ᔽ�ɂ͋ł܂��͔����̌Y�������ۂ����邱�Ƃ���߂��Ă���B���������@�������_�̎��R��ۏႵ�����@�Ɉᔽ���邩�ǂ����������x�������Ă������A�ō��ق͈�т��č����̗�����Ƃ��Ă����B�ō��ٔ����̑O�Ⴊ���҂̍l���ƈقȂ����Ƃ��A�ꔻ���Ƃ��Ăǂ̂悤�Ȕ��f�����ׂ��Ȃ̂��B���҂͏n���̖��A���R�Ƃ��Č˕ʖK��֎~�͌��@�ᔽ�ł��薳���ł���Ƃ̔������������B1968�N�̂��Ƃł���B���������̔����́A��㍂�قɂ����Ă����ɂ����������B
�@�N�@���Ƌ���ێ�I�@���l������ʂɋ������U������͂��߂��̂�1969�N�̂��Ƃł������B1971�N�@������ł������{�{�����₪�ĔC�����ۂ���鎖���Œ��_�ɒB�����B�u���N�͈��{�̔Ԃ��v�ƍJ�ł͂����₩��Ă������A���ہA�ō��ٔ�������u�N�A�ٔ�������߂��܂��v�ƒ��ڂ���ꂽ���Ƃ��������B�{���͂��̍��ɂ���������ƁA���₩���������͂���R�M��ттĂ���B�J��Ԃ���鎷�X�ȒE��ւ̗U�f�ƊO�I�Ȉ��͂�O�Ɂu�Ƒ��̂��߁v���邢�́u�C�����͕ς��Ȃ�����v�Ƃ����ĉ�������Ă��������̂����������B�������A���҂́A�Ō�܂Ő߂��Ȃ��邱�Ƃ����ۂ��Â����B���҂́A���̒e����]���āA�n���E�b�h�ɐ����r�ꂽ�}�b�J�[�V�[�����ɂȂ��炦�Ă���B�i���́u�f��l�̐Ԏ��v�̌o�܂̓��o�[�g�E�f��j�[���剉�u�^���̏u�ԁv�Ƃ��ĉf�扻���ꂽ�B�j
�@�����čĔC���ۂ͖Ƃꂽ���ō��قɋt������ٔ����͂��̌�ǂ��Ȃ������B�i�@�E�ɂ����Ă̊��������́A�@�C�n��̍��ʁA�A�����̍��ʁA�B�������ٔ����i���c�̂̍ٔ����j����͂������Ƃɂ���čs���Ă���B���҂́A���l�ƍق���͂��܂��Ė{���ł͂Ȃ��x���̉ƍق���ɂ܂킳�ꂽ�B����͏�ɓ��N�̏\���N���ǂ����B�u�����ٔ��v�����u�Y���ٔ��v����肽���A���ق���ٔ����݂�@������������Ƃ�������]�͐��ɂ��Ȃ����Ȃ������B
�@���̂悤�ȍٔ����̎��R�ƓƗ���N�Q���铝���x�z�͒f���ċ��������̂ł͂Ȃ��B�{���̖����`���Ƃɂӂ��킵�������ɊJ���ꂽ�ٔ����ɂ��Ă������Ƃ͑��}�̉ۑ�ł���B����ɂ��Ă��A�������̂�����i�@�E�ŁA���҂̂悤�ȍٔ����̑��݂������Ƃ́A�������Ɍ���Ȃ���]���������Ă����B���݂��ӎ����K�肷��B�������A���鑶�݉��ł��m���Ȕ��f�͂ƗE�C�������đ��݂��̂��̂��������ϊv���Ă������o�I�ȗ͂��K�v�Ȃ̂��B�M�O���т����Ƃ���`�ɂ���������₩�Ȑ������A����͈���Ă��l���ꂼ��A���҂̂悤�Ȑ�������������{�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�{����ǂ݂Ȃ��炻��Ȃ��Ƃ��l�����B |
|
 |
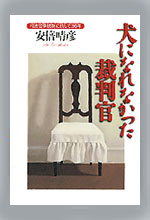 |
 |
�w���ɂȂ�Ȃ������ٔ����x
���{���F��
�m�g�j�o��
�{�̉��i1500�~
���s2001�N5��
|
 |
 |
 |
 |
 |
| �@�M�ҏЉ� |
 |
��c�@��
��t�B���s����A�����a�@�ŕa����S���B�ߋE�����Ō���w�Z�Z�������߂�B���̏��]�́A�S�̈�̍L���Ɩ{��ǂ܂Ȃ��Ă����̖{�̓��e���悭������ƕ]�������B��t�A��Â̎Љ�I�ӔC�ɂ��Ă̔����������B���߂Έ��ނقLj��߂�Ƃ��������ł�����B |
|
|
 |
|
|
|