 |
 |
本書は、朝日新聞(1998.9.6−1999.8.29)と『図書』(岩波書店、2000年7月−2001年6月)に連載されたコラムを集めたものである。私は、朝日新聞の日曜日、書評欄の片隅にあるこのコラムを毎週心待ちにして読んでいた。日本の近代文学といわれる作品をとりあげて自由自在に料理するその手腕が、主観的でありながら時代背景を的確に捉えていて、見知った作品を別の角度から評論してみせてくれる手際の良さに感心していたからである。
筆者は少年時代、読書家ではなく愛書家であった父の多くの蔵書を苦々しくみつめて、文学嫌いになっていたという。文学が面白くなったのは、文学を「鑑賞しなくてもいい」という発見をしたときからだと語る。そのとき、作品を書かれた時代背景から読み取る方法を知ったようだ。
たとえば松本清張の『点と線』では、「松本清張は決して『社会派』ではなかった。(中略)彼は高度成長時代の果実の分配の不平等にのみ執着して、その時代精神を『嫉妬』と『恨み』に因数分解した作家である」と断じて、以下のように続ける。「清張は現実の時代精神をえがかなかった。彼の内部にひそんだ強い動機に合わせて戦後時代と高度成長期をえがいた。それは彼自身の人生観を紙上に定着したということにほかならず、その人生観と現実との乖離が目立たぬうちは読者を引きつけ得たのであり、それはおおむね1964年の東京オリンピック頃までのことであった」こう書かれては、清張ファンの一人としては寂しいかぎりだが、肯かねばならない理を多く感じることができる。
本書では59の作品を取り上げているが、このようにすべての作品を時代精神の証言として捉えている。それは独断ではあるが決して的外れではない。そして、簡潔な断定調が不思議な説得力をもち、納得させられてしまう文章のたくみさがある。たとえば、志賀直哉『小僧の神様』で、貴族と区別された小僧「仙吉」の名は、大衆化した社会である戦後の向田邦子『あ、うん』の主人公の名として残されたと結論づける。
漱石『三四郎』、康成『伊豆の踊り子』、実篤『友情』、吉川英治『宮本武蔵』、吉野源三郎『君たちはどう生きるか』など青少年期の私を揺さぶった作品へのあまりにサラッとした批評に、少しの不満は残るものの、不思議と楽しい。それは、おそらくこうした問題を論じること自体が、文学が教養の一部と思われていた時代を共有する筆者との連帯感であり、その時代の懐古につながる思いのゆえだろう。今のように文学が教養でなくなってしまい、社会が共通の話題をなくしてしまっていいのかという思いを強くする。また、筆者の指摘するように、私たちの少年時代(戦後初期)も、童心が尊ばれ母性の憧憬が詠われた大正時代の価値観を引きずったものであったことをあらためて思う。 |
|
 |
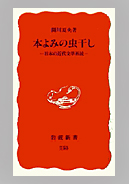 |
 |
『本読みの虫干し』
関川夏央著
岩波新書
本体価格780円
発行2001年10月
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|