 |
 |
ハンセン病訴訟は、政府が控訴を断念することで一応の政治的解決に至ろうとしている。しかし、そうした差別法をどうして長期に温存してきたのかという問題は、われわれ国民一人一人に問われている。
私が「らい病」を意識したのは、子どもの頃観た「ベン・ハー」という映画でであった。奴隷の苦役から解き放されたベン・ハーがみたのは、ラザレットで差別や迫害に堪えながら社会の片隅で暮らす母と妹であった。その後読んだ北條民雄「いのちの初夜」や『民主文学』の冬敏之のいくつかの作品からも、差別に対する怒りよりも、悲運な人たちの苦しみしか汲み取ることができなかった。同じ頃医学部の講義で聞いた、「らい病」は、感染力は弱くむしろ問題は誤解にもとづく社会的偏見だということだったが、それでも私は動かなかった。30数年前のことである。
松本清張原作、野村芳太郎監督の秀作『砂の器』が上映されたのは1974年だった。しかし、その後テレビドラマ化された同名の作品では、主人公の父親は「らい病」ではなく「精神病」ということに変わっていたと思う。「ハンセン病」を描くことは即差別を助長するというふうに考えたのだろうが、そう考えるのも肯ける国民的土壌があったのも事実だろう。
私も、数年前に本書を読むまで、「ハンセン病」に関する知識の乏しかったことを思う。国際的な体面を第一に考えた政府、光田健輔というボスに学会支配をゆるした医師・医学者たち、療養所に献身する人たちの美談を話題にしても断種・避妊手術などを知らせなかった報道関係者たち、そのほか国民一人一人が、その責任を反省すべき問題だったことが、いま明らかとなった。「少数者」ということで人の権利を封殺してしまう問題は、たとえ、その最大の責任が国家権力であったとしても、各人がよくよく考えてみるべきことである。本書を熟読することは国民のひとつの義務であるようにも思う。 |
|
 |
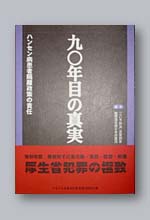 |
 |
『九〇年目の真実』
「らい予防法」違憲国家賠償請求西日本弁護団・編集
かもがわ出版
本体1,600円
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|