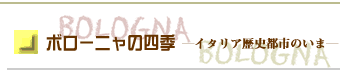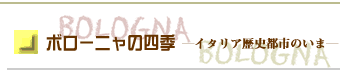|
〈イタリア新幹線とは?〉
最近では、私もイタリア鉄道の遅延は常識と考えるようになってきた。
それにかわって早さと正確さで救世主となりうるのか、いまイタリア新幹線の工事が始まっている。イタリア語でTAV(タブ、Trasport Alta Velocita)、文字通り高速輸送、高速鉄道である。
計画ではボローニャの市街地に入る手前から、地下トンネルに入る。その地下トンネル工事現場を見学する機会があった。まだ、新幹線について一般には紹介されることが少ないと思われるので報告してみたい。
新幹線は首都ローマと経済の中心地ミラノを2時間で結ぶ新路線である。
従来の鉄道線路の長さは、手元の時刻表で確かめると632kmである。不思議と言おうか2で割った316kmのところにフィレンツェがある。まさに中間点である。ボローニャはフィレンツェからミラノ寄り97kmのところである。
新たな幹線を直線状に結ぶのであるから、距離も短くなり600kmを切るとのことである。
見学がてら聞いたところでは、ローマ、フィレンツェ、ミラノが停車駅のようである。確かに観光客が多いことでは、フィレンツェはずば抜けている。
私の地元でも新幹線の一部車両の「名古屋飛ばし」が話題になったが、ここも「ボローニャ飛ばし」になるのである。それにしても全く停車を予定しなければ、地下トンネルを掘って、現ボローニャ駅に接近する必要もないので、やはり少しは停まるのであろうか。
完成年度は2007年度のようであり、「こだま」クラスは止まるかも知れない。イタリア人でも、実現そのものを予定通りと信じている人は少ないので、もう少し時間が経たなければ分からないのが実際のところであろう。
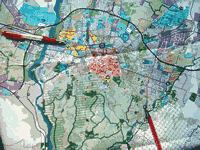
新幹線都心部地下トンネル工事、
右のペン先からチェントロ上の○を経て左までが地下。

フィレンツェからボローニャ5.5km手前のサン・ルフィッロ駅付近。新幹線はこの右手から地下トンネルへ。
〈地下トンネルで現ボローニャ駅に接近〉
そうは言っても「イタリアはやはり凄い」と、私は思う。地下トンネルで現ボローニャ駅に接近である。
日本は、高度経済成長のなかで人と物の往来は激しくなり、新幹線が建設された。やがて成田・関空が建設され、中部新空港も開港しようとしている。
その昔、騒音や振動などによる公害問題は深刻化し、大阪空港騒音訴訟や新幹線公害裁判が提起された。
新幹線公害裁判との関連でいえば、東京から名古屋へ接近する同市南区でこの被害は極致に達していた。
もと私の同僚の数学教師も、線路そばに居住し当時安眠することができなくなり、とうとう50代で悲しい死に至った。その式に参列したことを思い出す。20年は前のこと。いまは裁判を通じてある程度の減速が実現している。
ところで減速が問題になるのは、人口密集地を高架・高速で走らせるからである。
人口216万人の名古屋に対して、ボローニャは37万人である。比較すれば実に牧歌的と言ってもよい。
そのボローニャのチェントロ直径2.7kmを倍にした5.5kmあたりの郊外からの地下への進入である。確かに費用はかかる。しかし地下を走らせれば騒音問題は起きないのである。
どういう議論でここに至ったのかは私には不明である。しかし現実の行為は、人間への配慮に満ちたものであることは間違いない。
そこが日本に比べ、イタリアの違うところであり、さすがだと考える。日本ならさしずめ建設費用の問題が取上げられ、肝心の人間のことが置き去りにされてしまうところである。

工事現場の隣はいくつかの団地がある。

堀割でここから地下トンネル工事、
終わればフタをする。
〈近隣住民への工事内容の理解を求める〉
しかもフィレンツェからボローニャへの接近路は、2つの丘に挟まれた狭い区域を現・鉄道路線と並行して走ることになる。
ボローニャ駅から5〜6kmのところでは、密集状態ではないが住宅もある。工事は一部分の堀割で始まり、終われば完全にフタをして地下トンネル状態になる。
それでも工事中には様々な問題も起きてこよう。こうして土曜日を中心にした近隣住民への説明見学会の開催が繰返されている。
私が参加できたのも、こうした近隣住民への見学会へ誘っていただいたからである。3月27日(土)10時半から2時間位である。1班が帰ってきたので、1回目は8時半位から行われたのであろう。
団地の近くまでマイクロバスで迎えにきて、工事の現場事務所で安全帽、安全靴、安全服を着用し、現場に向かうのである。男性が多かったが、年輩の女性や若い方もいた。列の先頭に立ち熱心に質問をしていた。
工事は、スペイン1社とイタリア2社による共同企業体の施工である。トップはスペイン人のようである。工事の中身さえ押さえておけば、イタリア人であろうとなかろうとそれは問題ないとおおらかに思えた。このあたりの感覚は日本とは違う。
ついでに余談だが、ボローニャには薬局は12あり、従来は市役所が公的管理を行っていた。これを現在はドイツの民間会社に委託をしているとのことである。すでにEU・ヨーロッパ連合の合衆国の1つがイタリアという風に感ぜられる。
それはともかく往来2本のトンネルはボローニャ駅に向かって800mほど進んでいる。工事は機械が行っているとの言葉どおり、最先端の掘削部分で5〜6人の作業員がいる程度であった。
我々が近づくと、説明の声が聞こえにくいのを配慮して一旦工事を中断してくれた。このあたりは大事な近隣住民に来ていただいたという、そんな感じである。

地元住民と見学開始、右は前方ボローニャへ・左は手前フィレンツェへ向かう。

最先端部は僅かの人数で工事。
〈ボローニャをとりまく交通計画のあり方〉
ことのついでに、いまボローニャでは交通計画のあり方、すなわち都市の将来計画の琴線に触れる内容での意見対立があり、そのことが重大な政策上の争点になっていることをお伝えしておきたい。
すなわち歴史的な経緯から様々な社会的インフラ整備は、ボローニャ市を中心に行われてきた。
このため、例えばボローニャ市にある公立病院には、周辺部からも相当の来院患者があるのが実態である。
またボローニャの産業と不可分であった水資源管理などは、すでにHERAという第3セクター(電気ガス・水・環境)を通じて広域行政が行われている。
つまり現実には相当広域的なエリアを対象にした、住民サービスの方向が追求されている。
このために20km圏の広域的な交通網整備を行う。20km付近には自動車を置き、都心部には12分で到着可能な公共交通整備を行う、というのが一方の考えである。この範囲は現ボローニャ県程度が想定でき、人口は90万人である。
他方、現ボローニャ市に接続しているコムーネの範囲を目安にやや小幅な地域を、今後の交通計画の根底に置こうとする考えである。
現在ある重要な施設である「ボローニャ空港」と「ボローニャ国際見本市会場、フィエラ」という比較的近くに所在するこれらを結ぶ地下鉄を中心とした交通計画である。人口60万人弱を想定した地域である。
もちろん両者ともこれらとあわせて環状線や通過交通の高速道路の計画もなされている。
日本では高度成長期、都市への人口集中と拡大の時期に、中心となる都市へ向かう交通整備はできたが、周辺地域同士への整備はおろそかになり、その弊害が指摘されてきた。
つまり車があれば横へも行けるが、そうでなければ大変不便なものである。文化施設の利用を考えても遠くの中心市へは行けても、近くの隣町へは車がないと行けないという始末である。
これは単に交通問題に止まらず、生活や文化の享受に関わる根本的な生活の質の問題にもなってくる。
ボローニャでもまさしくこれと同様の状況に直面し、いまあるべき姿が問われているのである。
連載第25回「大学の街、ボローニャ」で、ボローニャ大学がボローニャへの一極集中ではなく、フォルリ、チェセナ、ラベンナ、リミニといった州内の他の都市への学部分散を図り州全体の学問的・文化的底上げを図っていることを報告した。
ボローニャとエミリア・ロマーニャ州の今後のあり方をめぐる議論と実践はいろんなところに及んでいることが分かる。
先にあげた見解の違いでは、前者がボローニャ県(左派)を中心とした考えであり、後者がボローニャ市(右派)の推進している考えである。
この意見の違いは一方(市)の行政執行に対する他方(県)の裁判所への執行差し止めの仮処分申請という大変な事態である。やはり6月の選挙結果により、次にどう展開するのかが決まってくるようである。
*ボローニャ空港のことをひと言。滑走路の拡張工事のため、4〜5月は閉鎖のようだ。
この時期は、110km離れた代替のリミニ空港からバスで乗り入れるしかほかない。以前から予定されていたようで、決して今年1月にセリエA、ボローニャに移籍してきた中田選手を訪ねる日本人の多さというわけではないと思うが・・・。

近くは春の装い、団地の庭で。

広域自治体ボローニャ県のパンフ、
大都市の交通計画。
|