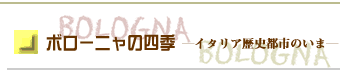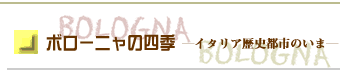イタリア列車に貼られたステッカー
「クリスマスと新年おめでとう」

マドリッドを中心とする地図に日本は出てこない

トレド大聖堂
〈始めてのスペイン・マドリッド〉
機上からみる地中海は雲ひとつなく素晴らしかった。1週間ほど前には、「マドリッドはボローニャより南にあるが、標高があるので冷え込みは厳しいですよ」と言われていた。
確かに地図でも667メートルの記載があり、一帯は高原状である。当たり前のこととはいえ、標高による温度差は想像が難しい。厳しさを覚悟し完全装備した上での、快晴の空は予定外で、むしろ暖かすぎる程であった。
機内誌のイベリア半島中央部・マドリッドを中心とする地球儀を模した地図には、日本は出てこない。日本で見る日本を中心とした世界地図にも、おそらくスペインやポルトガルは端のまたその端に顔を見せるかどうかであろう。
日本からイタリアも遠ければ、さらにその先にある国はもっと遠いに違いない。その遠い国スペイン・ポルトガルを通じて、日本が安土桃山時代にヨーロッパ文明に接触し、新たな対外関係を結んでいったのには不思議な感慨を持つ。
ともあれ、内陸部の大都市、人口290万人のマドリッドに入った。
街の雰囲気は、イタリアとはどこか違う。何がどう違うのだろうとの思いを抱きながら、滞在する都心地へ地下鉄で入る。地中海の東西の違いとともに、歴史の中に活躍した時代の違いや様々な要因があるのではではないのか、と思った。
行き来する人々の相貌に明らかな違いも感じる。
もともとのイタリア人、スペイン人に加え、一方はアフリカや中近東、バルカン半島からの来住者で構成され、他方はアフリカに加え、中南米のスペイン語圏からの来住者も含めた構成となろう。
スペインが大航海時代に活躍した1500年前後には、他方のイタリアではヴェネチィア・ジェノヴァ・フィレンチェなどの都市共和国の商人がスペイン・ポルトガルの王室に接近しその活躍を支えたとしても、同時にその富はいわゆるイタリア・ルネッサンスの興隆に注がれていた(注1)。
さらにはイタリアでは第21回で報告した「未回復のイタリア」を除けば、多くの領土は1870年のイタリア統一にいたるまで都市共和国による分立はあったとしても、イタリア人による支配が続いていたのではないのか。
一方のスペインはキリスト教やイスラム教などの「半島を支配した多数の文明が、有史以来栄枯盛衰を繰返して入れ代わるなど…波瀾万丈の歴史がその背景」にあろう(注2)。
この当たり前とも言えるトーンの違いが、人々の相貌に止まらず、街の持つ雰囲気の差異につながっているのではないかと思った。
翌日は1986年に世界遺産にも指定されたトレドをまわった。1561年マドッリドに都が建設される前の古都であり、マドリッドからは地下鉄を乗り継ぎ、さらにバスで1時間余を要した。川に囲まれ、丘の上に建設された要塞都市である。
もう1日はマドリッドのプラド美術館に入った。年末で日曜日の美術館は、入場料無料でクリスマス休暇を楽しむ多数の市民であふれかえっていた。年末・年始の休暇を利用したと思われる日本からの多数のツアー客も見られた。
一部を垣間見たマドリッドへの年末の小旅行であった。それでもイタリアとはまた一味違いそうなイベリア半島の姿に、新たな感慨を抱いた。

トレドの丘から下の街を臨む

マドリッドの街角風景

スペイン名物、パエリア
〈慌ただしく飛びかうニュース〉
滞在中良好だった天候も崩れかけていた。イタリアのテレビの天気予報では、ヨーロッパ一円の地図がでる。西の天気がやがて東に移る。
スペイン・フランスの天気は、何時間かを経てイタリアになる。ローマ空港では、視界不良の霧雨状のなかを着陸した。
イタリアの地を踏んでほっとするのは、慣れ親しんだ土地であり、多少は理解できるようになった言葉の違いであろうか。そのイタリアでは慌ただしいニュースが飛びかった。
【Blackout(停電)】
まずBlackout(停電)である。
列車でローマからボローニャに帰る車中のアナウンスであった。列車は、ローマ18:30発の指定席を予約していた。ローマ・テルミニ駅につくと、少しずつではあるが多くの列車が遅れている模様であった。
予定1時間前の17:30発が、18:10発、40分遅れで出た。遅くなることを予感し、無理やりそれに乗った。予定外だといわれて更に追加料金を支払った。フィレンツェの手前あたりに来た時、ローマ=ナポリ間の全線停電による運行中止の放送があった。
当初の列車が遅れて出ているのか、全部出発取りやめになったのかは定かではない。原因もよくわからない。危ういところで、無事ボローニャへの帰着となった。
確か9月にも、イタリア全土の停電があった。イタリアはフランスからの全面的な電力輸入によって存立している。それがスイスで送電線の断線事故を起こし、イタリア中が真っ暗闇となった事態である。
統合なったEUを考慮にいれたとしても、電力の全面輸入という発電事業のあり方や緊急時の対応といい、おそらく日本では考えられない問題が潜んでいることを感じさせた。
【プローディEU委員長】
そしてプローディEU委員長宅への小包開封中の爆発物事件は、ボローニャの名を世界に駆け巡らせた。
元ボローニャ大学教授のR・プローディ氏は、1996年総選挙で中道・左派連合「オリーブの木」の勝利のあと98年まで首相を務めた人物である。その後99年に現職に就任している。
最近の日本の報道でも、「来年末の任期終了後は、ベルルスコーニ首相に対抗する中道左派の指導者として(イタリア)政界復帰を期待する声が出ている」(注3)とのことである。
その氏の居宅は、ボローニャの象徴とも言える「2つの斜塔」から遠くない、カペッキ教授宅から言えば更に近いところにある。
イタリア紙には、「プローディ、騒ぎの中に帰宅」「EU委員長は今年もオリーブのため乾杯に戻る、そして家族のいるところへ」と記されていた(注4)。
【Parmalat(パルマ乳製品会社)と中田選手】
年末・年始にかけてサッカーセリエA・パルマの中田英寿選手が、当地のチーム・ボローニャに移籍するニュースが飛びかった。手にした新聞には何ヶ所かにわたり、移籍の記事がある。
「中田は、きょうパルマを出ることを決着させるだろう」(注5)。すでに第24回のサッカー報告でボローニャ強化策の観測記事を指摘しておいた。その関連である。パルマ=ボローニャはわずか80キロちょっとの隣町で、市民も活躍ぶりをよく承知している。
むしろここではなぜパルマが中田を手放すことになったのかについて述べておきたい。
サッカー報告の12月7日時点でパルマは18チーム中、5位、ボローニャは12位である。中田にとってはそのパルマで出番が少なかったこと、ボローニャのマッツォーネ監督(ペルージャ当時の監督)の招聘なら渡りに船だったかも知れない。
しかしそれに加えてもっと要因はないのかである。選手のゼッケンには親会社の「Parmalat(パルマラット)」のネームが入っている。
「Parmalat」とは、牛乳・チーズ・ヨーグルトなどを生産する、イタリアのみならずヨーロッパ有数の乳製品会社である。当地では、連日のように、その親会社の投資した資金回収が困難となり、倒産の危機と回収不能となった疑惑追求・救済策が報道されていた(注6)。
この際、高額で獲得した中田を放出して、資金を確保したい思惑もあったのではないか。
本人と親会社の意向が合致して、今回の移籍となったものと考えることができよう。こうして後半戦の始まる1月6日直前の1月3日、中田の同席した正式の記者会見になった。
サッカーに止まらず、イタリア経済の重要な断面を露呈するニュースと見ることができる。

プロ−ディEU委員長関連の記事

中田のボローニャ移籍の記事
〈マッジョーレ広場の厄落としと新年行事〉
年越しは、マッジョーレ広場の厄落としと新年を迎える行事であった。巨大な人形模様の張りぼてが大晦日の広場に立ちあがっていた。午後8時から12時近くまで、ステージでは音楽やトークが続いた。
平常とは予想もできない人波が、あっと言う間に膨れ上がっていく。カウントダウンの始まるはるか以前に、もう立すいの余地のない逃げ場のない広場の人・人・人であった。
点火された炎は大きく舞い上がった。あちこちで爆竹がなり、ビンがそこここで打ち捨てられ、狂気の如き様の中で、時は過ぎていった。過ぎ去ってゆく過去を遠くに追いやり、迎える新年を歓喜で呼び込む。洋の東西は違っても心は同じだと実感した。
しかし、ビン類の投げ割りは極めて危険であり、どこか同調できない違和感を持った。
またやや元気のない花火を見るにつけ、ここで日本の豪快かつ優雅ともいえる打ち上げ花火ができないだろうかと思った。そうすれば極めて知名度の高いTOYOTA、HONDAやSONYやCASIO等とはまた違った、日本を見てもらえるのではないかと思った。
そして喧騒の中で気がついた時にはもう遅かった。ポケットの財布とカバンの中の品物は失われていた。翌日、つまり元旦早々の警察では、担当官が極めて多数の盗難届があったことを白状していた。
これもボローニャの現実であり、自身にとっては慣れによる甘さを戒め、残された生活への警告と受け止めることにした。
(注1)「高校世界史B新訂版」(2002)鶴見尚弘、遅塚忠躬、実教出版、p.99〜101参照。
(注2)「世界遺産を旅する2 スペイン・ポルトガル・モロッコ・チュニジア」(1997)川添智利、山田幸正監修p.8〜9参照。
(注3)「中日新聞ホームページ2003年12月27日」
(注4)"La Repubblica martedi 30 dicembre 2003" Bologna Cronaca p.III,写真7は同紙p.7。
(注5)"La Repubblica martedi 30 dicembre 2003" Bologna Cronaca p.vI,写真8も同じ。
(注6)疑惑解明の進展していない段階では、報道各紙によって負債総額も異なってくる。イタリア人の友人の1人は、"la Padania Mercoredi 7 gennaio 2004",p.4の全債務69.69億ユーロ(約9千億円)に対し、2倍近い120億ユーロ(約1兆6千億円)という桁外れな数字になることを指摘していた。日本の報道でも「カリブ海の租税回避地、ケイマン諸島の子会社が保有するはずの手元資金が存在しない」ことが判明し粉飾会計が発覚したことを伝えていた。「アサヒ・コムhttp://asahicom/sports/soccer/tky200401020103.html(共同 2003年12月23日)」。