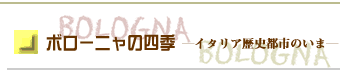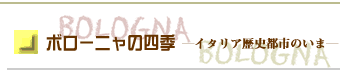大学へ行く起点となるボローニャ斜塔、空に映える

この両側が大学キャンパス、学生のバイクも多い

大学本部入口
〈数字でみる学生の街、ボローニャ〉
今回はあらためてボローニャの特質の一つである、“学生の街”を数字で見てみることにした。ボローニャ市の2つの資料をもとに整理した(注1)。年度は9月から始まるので、例えば2000年から2001年にかけての教育年度が、2000-2001年度と記されている。卒業は随時行われているようであるが、多いのはやはり6月頃であろう。こうして各年における卒業数が記されている。約10年間分のデータである。
【学生住所地・大学所在地別学生数】
■ ボローニャ大学生の8割、8万人がボローニャ校舎に登録 ■
まずボローニャ大学の実像をつかむには、図表1を見ていただくと良い。大学の全学生は、2000-2001年度で99,130人であるが、ボローニャ校舎には8割の79,916人が登録している。残り2割が同校舎以外であり、フォルリ校舎7,316人、リミニ校舎4,286人、チェセナ校舎4,224人、ラベンナ校舎3,388人となっている。
校舎のある街の位置関係を少し説明しよう。
ボローニャは南北に走る鉄道ヴェネチア〓フィレンツェ線と、北西ミラノ〓南東リミニ・アンコナ線が交叉している。従って、内陸都市ボローニャから南東に約110キロでアドリア海を臨むリミニの街に至る。
この線上に、ボローニャから近い順にフォルリ、チェセナがある。そしてフォルリとリミニに対する三角形の頂点の位置が同じく臨海都市ラベンナである。すべてエミリア・ロマーニャ州にある。
ボローニャ大学は、こうした都市への学部分散を図っているのが特徴的であり、極めて重要な点だと思われる。ボローニャへの一極集中ではなく州全体の底上げを狙っている。
ボローニャ市の資料でもそのことを次のように評価している(注2)。
「2000−2001年度のおいて実現した新学部の設立(リミニとフォルリの経済、フォルリの政策科学)、ディプロマ新コースの開設、そしてその他の大学分割は、大学改革のスタートにおいても、今後の入学数の復元促進を将来に予感させながら、ボローニャ人の高等教育機関への人間形成の場の提供を新たに拡大した」
なお、何故ボローニャの南東方向への進出なのかについては、察するところエミリア街道の、その反対方向30数キロにはモデナがあり、さらにそのすぐ先にR・エミリアがある。そこには「モデナ並びにR・エミリア大学」がすでに存在しているからであろう。
いまボローニャ校舎だけを取ってみると、学生の52%がエミリア・ロマーニャ州に住所地があり、さらにその半分はボローニャ県となっている。同時に北イタリアや南イタリアを含めたイタリア全域から学生の47%が集まってきていることもわかる。
多くの大学が設立された今日では、昔日と比較しボローニャ大学の持つ比重も変わってこよう。それでもエミリア・ロマーニャ州とイタリア全土に注目される大学には違いはない。
ともかくも8万人近くの学生がボローニャ市に通学し、関わりを持っていることになる。このうちどの程度の学生が現実にボローニャ市に居住しているかはこの数字では不明である。しかし、街づくりにとっても大きな要素であることは間違いない。
図表1 ボローニャ大学 学生住所地・大学所在地別学生数
【学部への登録学生数推移】
■ 全学生は10万人近く、しかし大学に滞留する学生が増加 ■
次に登録全学生数の推移である。
1990-91年度を100%とした指数は、1996-97年度に最大でその後一旦低下し、2000-01年度には127%を示し10万人台に回復しつつある。
しかし1年生の登録は1990年代半ばの1万8千人の大台には回復していない。学部分散に入学数の復元促進の期待が持たれていることの意味合いであろう。それでも1990年代を通して1万6〜8千人が入学してきている。
一方、入学数が増加しないで状態で、全学生が増加し1年生の割合が低下していることは、大学に滞留する学生が増えていることを意味している。
ここにもボローニャ大学の学生が抱えている問題が潜んでいるのかも知れない。男女比は90年代初めに拮抗し、その後は女性が53%の多数派へと逆転している。
なお統計資料はついてはいないが、記述では次の指摘がある(注3)。「2001-2002年度の状態は、一方では入学者数の本質的に不変なところを示し、他方ではより高齢者人口の階層の入学(30歳を超える年齢の第1学年への入学数約7%)を奨励しているようにみえる」。
こうしたところに、もう1つの大学改革のねらいがあるのかも知れない。
図表2 ボローニャ大学 学部への登録学生数推移

文学・哲学学部の表札

法学部の入口で

学内の階段手すりにも彫刻
【学部別学生数、卒業者数】
■ 20学部を擁する総合大学、卒業者数は10年前に比べ1.75倍の1万人を突破 ■
ボローニャ大学はもともとは、法学と芸術の2学部からスタートしたとのことである。
芸術の精密描写はやがて人間の外表面に止まらず人体の内部構造の正確な把握、つまり医学分野の独立まで進んでゆくとのことである。今でも数世紀まえの様々な、しかもあまりにもリアリスチックな人体の内部模型が大学図書館に展示されているのには驚く。こうして学問の分化が進んでいったものと思われる。
それはともかく現在は20の学部を持つ総合大学となっている。図表3、4はボローニャ大学2000-01年度の全登録学生の多い順に並べたものである。文学・哲学、経済学、政策科学、工学、数学物理・自然科学が年間1,000人を超える入学者がある。
最小は建築学の創設2年目で、イタリアで言えばやや意外な感じを持つ。実に多彩な学部を持つ総合大学である。参考までに日本人学生は当年度12人であり、文学・哲学が5人で最高である。
学士・資格取得者の総数も入学者の多い学部と当然相関がある。厳密な意味での卒業率ではないが、該当学部の1年生と学士・資格取得者の比率を示しておいた。
一般に入学は易しいが卒業は難しいというイメージからすれば、全平均が60%というのは私にはやや意外な感じを持った。
これはもう一方の図表4の卒業者数推移を見れば、もっとはっきりする。1990年に5,731人であったのが、2000年には1.75倍の1万人を突破している。
語学・外国文学、文化財保護、心理学、運動科学、生物工学などが新たに卒業生を出していることもあるが、総じてどの学部も卒業生が増加している。そうした意味では、大学自身の内部改革が進行していることも確かであろう。
卒業者数から学生の選好基準の変化を読み取るとすれば、特に増加の著しい分野は経済学、工学、政策科学、数物・自然科学の学部である。伝統的な文学・哲学、法学の学部に併せて、ここにボローニャ大学生の向かう目があるように思われる。日本の潮流と比較しても充分肯ける内容である。
図表3 ボローニャ大学 学部別学生数、卒業者数
医学・外科が−149人で注目を引くが何故マイナスであろう。卒業への厳しさなのか、ボローニャ市は控えめに次のような指摘をしている(注4)。「外国人の間で、より強く求められている学士号は医学・外科である。2000年には4人に1人の外国人がこの専門職資格の学位を授与されている」
図表4 ボローニャ大学 学部別卒業者数推移
【学部別、予定年数超過学生】
■ 予定年数を超えた学生は全学生の41%の多さ ■
さきに登録学生数推移のなかで、大学に滞留している学生が増えていることを指摘した。
そこで図表5により学部別年数超過学生をみてみよう。これは法学など多くの学部は予定年数4年であり、医学・外科は6年と、学部によって若干の差があることは日本と同様である。従って、事情は別としてこの年数を超えて在学している者をここでは超過学生と呼んでいる。
全大学平均が41%であり、法学56%、獣医学51%と学生の過半を超えている。法学は予定年数内学生5,703人に対し、年数超過学生は7,188人と、実数でも極めて多い数字である。
この超過学生の多さが、日本とは大変な事情の相違である。従って、在学の課程で学業を放棄してくるものが多いことも当然予想されるし、先にみた卒業率はこの人数が考慮されていないので、本当の意味ではもう少し低い値となって来よう。
図表5 ボローニャ大学 学部別年数超過学生
【入学のために提出されたタイプ別卒業資格】
■進学率の大幅な上昇、出身学校の大きな変化技術学校・職業学校からの進学は激減、理系・文系高等学校の増大 ■
次に入学生が提出した卒業資格のタイプの変化である。
すでに第20回「ボローニャの人材育成に異変?」で、後期中等教育の学校種別入学生徒数に大きな変化が起きていることを報告した。すなわち入学生総数がわずか10年余りで67%へ減少し、商工技術学校(49%)や専門職業学校(56%)に至っては激減である。
これとの関連から図表6を見る必要があることは言うまでもない。総数ではわずか減少しているが、96%であり、「その他の資格」も90年代半ばに多かったことはあるが、最新値では変動はない。従って後期中等教育卒業資格による総数の変化もそれ程ではない。
つまり、後期中等教育入学生徒数の大幅な減少にもかかわらず、ボローニャ大学への入学数に大幅な変動がないということは、大学進学率が大幅に上昇している。そのことがこの10年間の間に起きていることを物語っている。
それとの表裏の関係となろうが、商工技術学校の卒業資格を持つ者の入学生は1,100人を超える減少、専門職業学校のそれは500人近い減少、そしてそれを補う理系・文系高等学校出身者の増大である。
その他の資格は、これら以外のディプロマ資格を持つもので、90年代半ばには増加しているが、10年前と比較した現時点では大きな数値の変化はない。
ともかくこの結果、10年間で技術学校・職業学校からの進学は激減し、理系・文系高等学校卒業生の比重は増大し、ボローニャ大学生の質を構成する内部構造が大きく変容していることが想像される。
図表6 ボローニャ大学 入学のために提出されたタイプ別卒業資格

さすが学生の街、本屋は多い

大学近くのコピー屋、1枚0.04ユーロ(5円)が多い

人数の割にはいかにも狭い学生食堂
〈イタリアの大学の不思議〉
一通り数字を見てきたが、もう少し体験したことを付け加えておこう。
それは、これだけの巨大な大学であるが、私には疑問がわいてくる点もある。他のイタリアの大学もかなり似通っているとは思うが、少なくともボローニャ大学では日本で想像するような“キャンパス”という雰囲気ではない。
しかし、ザンボー二通りの界隈は地域全体がキャンパスであるかも知れない。しかし日本のイメージとは違うのである。
教室は、想像ができない程の極端な分散配置である。文学・哲学学部に至ってはどこで収容するだろうと思える程の人数である。私のよく顔を出す教育科学部でも日本で言えば中規模教室が幾つかはある。
しかし1年生だけで857人、4学年で3千人近くを、どこでどう教育しているのか、不思議である。イタリアの建物も、うなぎの寝床といおうか、確かに外からは考えられないような奥行きの深さはある。
教授の研究室も同様である。1部屋の大きさはその昔、数百年前の建物構造から概ね決まっている。日本のように大スパンの大部屋の部屋も取りにくい。ましてや1教授、1部屋という大きさにはもったいない。部屋の大きさから、1部屋2〜3人、3〜4人が一般的な教授室になる。
不思議のついでに、身近に感じた研究指導のやり方(ゼミナール、演習)を紹介しておこう。
日本では文系・理系でやや違いもあろうが、戦後一般的に研究事項について集団的な議論・討論を通じて相互学習と、より高い次元に引き上げる作業が行われてきたと理解している。
直接にそのテーマに関して、あまり関心のない分野でも他人の報告・討論を聞く中で視野を広げる、ないしは予期せぬ質問に遭遇し、新たな視点での検討が求められる。集団討議にはこうした良さを持っていて、多くの高等教育機関でも採用されているのではなかろうか。
しかし、イタリア、少なくともボローニャの私の近くでは違うのである。あくまで、プロフェソーレ(教授)が一人ひとりの学生にあい対する関係となる。
それは教授に指導を求めている学生が何人いても変わりはない。一人ひとりが教授との対話を行う。こうして教授の予定時間がくれば、そこで打ち切りとなろう。
このため一方では、面会時間の席取りが始まる。9時からの開始(いまはもう少し遅くなったが)であれば、9時に行っていては遅い。
私はなんとか8時過ぎに顔を出す。特に冬場になると緯度も高いボローニャでは8時でも相当暗い。まだその時間は、顔見知りの数人が始業前の請け負った清掃作業に余念のない時間である。そして自分で掲示板に席取りの紙をはり、自分の名前を書く。こうして初めて待ち時間のない指導を受けることができる。
9時過ぎに部屋から出てきて、その紙をみれば20人は名前が並んでいることはざらである。20番目は何時に終わるだろうかと思いながら、その場を立ち去る。こうしてあちこちの廊下には待機する学生があふれている。
毎日ではないが大学の光景である。
(注1)Comune di Bologna"Relazione previsionale e programmatica 2003-2005"(2003),以下"Relazione"と略。Comune di Bologna "Annuario Statistico 2001"(2002), 以下"Annuario"と略。
(注2)(注3)(注4)前掲書"Relazione"p.15。