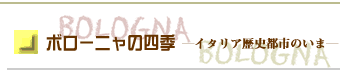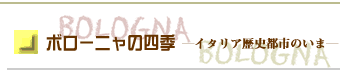秋に入ってから、一旦急激に冷えこんだボローニャ。一様に冬装束に替わっていく街の姿。始めての体験となるヨーロッパの冬。寒いという程ではないが、冷えこみが続いた。もう見かけなんか構っていられない、そんな思いをしていた。
それがここしばらくは一種「小春日和」という感じである。あの異常に暑かった夏とも関係があるのだろうか。
それでも、もう12月に入った。少し前からそこここの街路で、かけ渡されたイルミネーションの電球の点灯テストが行われていた。場所によっては、はしごを掛けて一人が登り支えるもう1人と組になり、電球が切れていないか点検を行う。別の場所では本格的な工事用重機を道路の真ん中に据えて行っていた。
「いつになったら、点きますか」というと、「今週の金曜日だよ」との答えである。それは11月28日であった。一斉とまではいかなかったが、街にイルミネーションが灯った。キリスト教最大の行事、クリスマスを迎えるそのセレモニーの最初のデコレーションであるかも知れない。
日本でも、住んでいた名古屋城の近くのホテルでは毎年この時期になると、樅の木のツリーを模ったイルミネーションが点灯される。デパートでは、ボーナス支給を当て込んだクリスマス商戦と称して、書入れ時とばかり一斉に売りにでる。記憶に新しいそうしたものと、ボローニャのこれは同じであろうか。街を歩きながら、そんなことを考える。
日常の生活範囲であるチェントロ内、いわゆる歴史的市街地区では、その主な通りでイルミネーションが点灯し、ショーウインドウの中もクリスマスを感じさせる赤白の彩りが並ぶ。もちろん売らんかなの思いが先に立つ、そうした雰囲気で無いことは確かである。
12月2日、マッジョーレ広場に通りかかった。ネプチューン像近くの石畳をはがして、そこに巨大な20〜30メートルもの高さの樅の木が立とうとしていた。クリスマス用の樅の木か、さすがやることは違うな、と思いながら近づく。
しかし樅の木の足元がいけなかった。根はなく、切られて尖っていた。つまりこの時期だけで、捨て去られてしまうものとなっていた。私には、巨大な立ち木だけに、それを扱う役所や人々の自然や環境への意識はどうなっているのか、ボローニャの環境意識に触れる思いがした。
 |
|
| ↑ボローニャ斜塔にネオンが灯った |
 |
 |
↑雨にけむる斜塔 |
| ↑インディペンデンス通りに灯ったネオン |
 |
 |
↑マッジョーレ広場横の通りもネオンが灯る |
| ↑マッジョーレ広場の樅の木にネオンがついた。左奥はインディペンデンス通り |
|
〈イタリア人はクリスマスをどう過ごす〉
イタリアで休日となる祝祭日は、どうなっているのかあらためて確かめた。
キリスト教にちなむ祝日が6回、その他には元日(1月 1日)、イタリア解放記念日(4月25日)、労働の日(5月 1日)の3回がある。合計9回である(注1)。
一見すると日本より少ない感じだが、1年間の休暇全体を見れば決してそうでないことがわかる。以前から土・日曜日はほぼ完全休みであるし、一般に商店は木曜日午後は閉店となっている。それ以上にヴァカンス等に行使する休暇は、日本とは比較にならない程の差異がある。
ともあれ12月は、クリスマス(25日)、聖ステファーノの日(26日)の2日間となっている。この他に休日ではないが12月の祝祭日に、聖母無原罪の御宿りの日(8日)、クリスマス・イブ(24日)がある。やはり最大行事はクリスマスであろう。学校は一般にクリスマスを挟む2週間が休みとなる点では日本とほぼ同じであり、労働者は1〜2週間の休暇となる。
クリスマスの過ごし方を聞くと、返ってくる返事は「家族とともに過ごす」というのがお決まりである。家族同士であらかじめ用意した贈り物を交換しあう。
知り合った女性教師に聞いてみた。「オーストリア国境がもうすぐという町、5時間も列車でかかるの」といいながら話してくれた。
その実家へ帰り、12月24日は午後7時頃軽い夕食をそろって取る。午後11時から12時ころ、教会へ出かける。祈りの後、深夜に家路につき床につく。そして25日の昼食がとても盛大だと言っていた。もうお腹一杯になるほど食べるのだという。
そして彼女の場合は、家族それぞれが贈り物を交換し合う。お父さんにはネクタイと上等なワイン。お母さんには選りによった香水とセーターのようだ。そして兄弟にも用意する。
「結構大変ね」と言いながらも家族の絆を確かめ、再会を喜んでいる感じであった。別の日に、彼氏には研究用の歴史書の厚い本を贈るという。
また、下宿の主人にも聞く機会があった。
「普通はどの程度の贈り物をするの?」「色々あるけど、50〜100ユーロ(1万円前後)位が多いじゃないの」との返事が返ってきた。
その50代の主人は、12月8日を挟む1週間をまず南部イタリアのカラブリア州の実家に戻って両親と過ごす。「食べてばかりなの」と聞くと、「いや寝てばかりだよ」と笑いながら答えた。クリスマスは奥さんの実家のある北イタリアのロンバルディア州へ出かけるつもりだという。
余談だが、その奥さんは10月半ばから2ヶ月間、南インドへのヴァカンス旅行に一人で出かけている。ご主人の仕事ぶりもそうだが、自営で設計業を営んでいるという彼女も一体いつ仕事をしているのだと思ってしまう。その点では余裕があるというのか、一種優雅でもある。
家族もあちこちにいると、クリスマスに一緒に過ごすというわけにも行かない。そうした場合は、12月8日の祝祭日に祝いと贈り物の交換を早々と行うこともあるようである。
こうしてみるとクリスマスに家族が再会しているのは、日本の年末・年始と同じであるかも知れない。とは言っても外で仕事を持っている下宿の主人でも、1〜2週間の単位で遠方まで帰省するのは年に何度かあるので、この点が日本とは大きく違うようである。
 |
|
| ↑商品もクリスマスを感じさせる赤白の彩り |
 |
 |
↑クリスマス用の小道具を売る |
| ↑飾りの人形、家族にあわせて組み合わせはいろいろ |
|
〈歳末消防訓練や多彩な文化イベント〉
12月4日、マッジョーレ広場では時ならぬ歳末消防訓練が行われた。日本では火災発生件数が最大となるのは一般に最も乾燥する2月であり、出初め式は年明け早々に行われている。
こちらではこの時期雨も多いので、日本ほどの乾燥ではないが、クリスマスという一大イベントを迎える前の訓練であろう。高所からの綱を使った救助訓練やボンベ火災の消火などの幾つかが行われた。それらもすべてこのマッジョーレ広場で行われる。
その広場に面し、つまりサン・ペテロニオ聖堂と向きあう形でポデスタ王宮殿がある。その昔に神聖ローマ帝国との対決を余儀なくされ、帝国から任命された行政長官に代えて市民が首長を選出し自由都市ボローニャとなった由緒ある建物である。その建物と背中あわせになっているのが、帝国に勝利を収め皇帝の息子を長期にわたり幽閉したエンツォ宮殿である(注2)。
そのエンツォ宮殿も普段は開かずの扉である。ところが12月4日から3月7日まで3ヶ月の長期の展示会が開催されている看板をみる。グリエルモ・マルコーニ、つまり無線通信の発明者である彼が、このボローニャ出身者であり、その功績を顕彰した展示会である。
「1874年イタリア人の父とアイルランド人の母のもとに生まれる。通常の学校生活になじめず、個人教育を受ける。…。」こうした説明で始まり、彼の創り出した電気通信技術の多くが展示されている。平常は、ボローニャ〜フィレンツェ間のマルコーニ家の邸宅に博物館が常設され、この時期には毎年エンツォ宮殿で展示会が開催されている。
成るほど、それでサン・ペテロニオ聖堂の裏手には、マルコーニの胸像も設置されているのか、と合点がいく。今日みる全世界的な高度情報通信社会の先駆者といえる人物である。
この展示会だけでも、音響デザインなど12月だけで10回ほどの企画が組まれている。さらに文化イベント案内には、音楽、映画、展示会、トーク、街の紹介、ツアー、そしてマッジョーレ広場での新年前夜祭が予定されている。
移民問題が深刻化しつつあることも報告したが、少し前にはサラ・ボルサの図書館を会場に「アルバニア移民の歌とトークショー」があった。積極的に市民に移民問題を訴えていく、時期に適った催しであった。
これらの多彩なイベントは、さすがヨーロッパ文化首都・ボローニャ2000を経た都市と思うに充分な取組みである。
 |
|
| ↑模型=図書館側からエンツォ宮殿(左)、ポデスタ王宮殿(右)を臨む |
 |
 |
↑エンツォ宮殿「マルコーニ・天才・未来」展示会 |
| ↑展示会でサンレモ音楽祭ポスター岸洋子(イタリア,1968)に出会う |
 |
| |
↑マッジョーレ広場では歳末消防訓練 |
(注1)坂本鉄男編「和伊辞典」(1988)白水社、p.477。
(注2)時田慎也「ボローニャ/パルマ/ポー川流域 イタリアとイタリア史の縮図」(2003)日経BP社、p.28〜29。「地球の歩き方 '03〜'04 イタリア」(2002)ダイヤモンド・ビッグ社p.370。