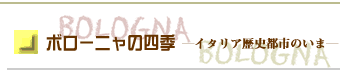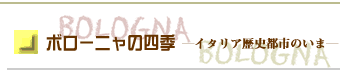10.24ゼネストポスター
「あなたの未来はあなたが守る」

執務中のルーチョ・サルチーニ氏、笑顔で応対

CGL・年金者組合州本部の看板(中央)
― ― ― ― ― ―
【質問の趣旨】
日本では以前は60歳になると、年金受給が開始されていた。しかし、これを65歳に後送りする提案が政府からなされ、すでに2003年から段階的に移行が始まっている。数年後には完全に65歳からの支給となる。また来年には政府が、掛金の1.5倍化、給付の24%削減を考えている。これに反対する大きな運動も起きている。
年金問題は日本でも大変関心が高い。イタリアではどの程度の提案がされて、今後の推移はどうなっていくのか大変興味のあるところである。日本のホームページ・WEBマガジン・福祉広場の読者を通じて、イタリアの現状を伝えたい。
【Q 1 : TV・新聞で年金改革についての報道がある.これまでの経過は?】
イタリアでも高齢者の人口が増えていることは確かである。このために1995年、つまり8年前にイタリアの年金受給者にとって大変重要な改革が行われた。このとき労働組合も合意の上で改革がなされ、将来を見越したものであった。
この時の改革は、それぞれの労働者が57歳から65歳の間で、いつから年金受給者になるかを決めることができるという内容のものであった。当然、受給開始年齢を57歳に決めた人は、年金額が低くなるし、65歳に決めた人は、それに比べて高くなる。
この間の総受給額は一定である。政府は国民のためにこのシステムとともに、その支出枠を保障した。年金は労働者から支払われる拠出金・税金などによりまかなわれている。
イタリアでは、この年金システムは国民にとっては義務的なものとなっている。高齢者になる時のために、この拠出金を支払うことが義務づけられ、現在働いている人が年金受給者の年金を支払っている。
このシステムは、今日、改革の必要性はない。なぜなら、年金支給総額はわずか数年前に予想されたものであり、年金受給者にとっては約束されたものだからである。
【Q 2 : なぜ政府は年金改革を行おうとしているのか?】
政府は、年金システムを大きく変更する政府案を決定した。これは57歳から65歳の範囲で受給開始年齢を選択できるという労働者の権利を取り上げて、2008年には一律65歳からの受給開始へと変更を強要するものである。
受給開始年齢を引き上げ、受給期間を短くする。しかも従来は65歳で高い水準の給付を受けたわけだが、その金額を引き下げるという内容である。
このことがなされる理由として、イタリアは現在巨額の対外債務を抱えているからである。今日、国の年金の支出枠は国民総生産の14%であり、現在の年金システムではその支出が特に増えることはない。
しかしイタリア政府は改革を望んでおり、法律を変えたいと考えている。なぜなら政府は巨額の対外債務を問題にしているからである。政府は国民総生産の10%〜11%に縮小することを望んでいる。
【Q 3 : 現行の年金支給の内容、及び改革の中身は?】
年金受給額は現在、57歳開始で年収の52%、65歳開始で70%、平均して60%が支給されている。1995年以前はこのようにはなってなく、1994年のベルルスコーニ退任後に、年収の何%という形で、一律化されたものである。
ちなみにイタリアでは平均が年収の60%だが、他のヨーロッパ諸国、例えばドイツなどは平均70%と高水準である。ベルルスコーニ首相は、現在のパーセントを変え、受給開始年齢を65才に引き上げ、そのうえ受給額を年収の52%に引き下げようと提案している。
さらに長期雇用を期間的雇用に移行させ、年収そのものを引き下げるとともに、年金支出を引き下げる考えである。そのために労働組合員と年金受給者は一致して反対している。年金受給者は、将来への不安を抱えている。
[補足] 確認したところ、年金額は支払済みの拠出金によって計算される。しかし、おおむね労働能率が低下し、賃金もやや低くなるであろう、その前段階の年間賃金を年収と考え、それに対する上記パーセントと考えてよいとのことである。
【Q 4 : 国民各層・団体はどのような反応を示しているのか?】
ベルルスコーニ首相の立場は、1994年と現在では大きく変化している。1994年は国会内で、約600議席のうち支持派議員は反対派議員を5議席だけ上回っていたが、現在は100議席上回っている。そのためとても強い力を持っている。
労働組合は年金受給者とともに、10月24日にイタリア全土で4時間の大規模なゼネストを予定している。ボローニャでも、午前10時ごろから、マッジョーレ広場での集会とその後の大きなデモを予定している。
【Q 5 : あなたは年金者組合の州幹部として、この問題をどのように考えているのか?】
いまこの問題の解決のために、懸命に努力している。何よりも多くの労働組合が一つにまとまって行動することが重要であると考えている。もし今回のゼネストによる成果がなければ、さらに次の行動を考えている。できれば、前回同様、ベルルスコーニ首相が退任することを望んでいる。
― ― ― ― ― ―
〈インタビューを終えて〉
労働組合の事務室に入った。建物のつくり方がそうさせるのか、日本のだだっ広いイメージとはおよそかけ離れた、落着いた一人部屋である。インタビュー中にかかってきた電話でみせる厳しい顔は、写真の笑顔とは対照的であった。
1年間の年金が、年収の60%が現行であるとの話には驚く。今年から年金受給の年になる筆者には、たしかそんな高い比率の説明ではなかったはずだ、と自分のパーセントを頭で計算する。まして、ドイツなどの高い水準の話が出てくるとなおさらである。
氏は、「ベルルスコーニ首相は、日本がそうであるようにアメリカ型の低水準にしようとしている」との見方を示していた。そうか水準からして日本はヨーロッパ型ではなく、アメリカ型なのだとうなずく。
今後の見通しを聞いた時、数ある産業別中央組織の労働組合が、統一行動をとれるかどうかが重要であり、また第二次、第三次の行動を考慮に入れていると強調していたことが印象的であった。

ボローニャ経済会議所
(商業・工業・手工業・農業)

斜塔〜マッジョーレ広場間のポルティコ

路地裏の景色