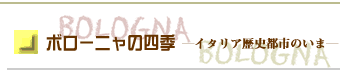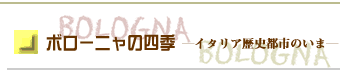|
今回の滞在目的の中心は、ボローニャが21世紀への挑戦をどのように考え、取組みを始めているのかを少しでも明らかにすることにある。私なりの結論は1年後に、どのような成果を持って帰れるかにかかってくる。いまは折に触れて、ボローニャ再生へ向けての過去・現在・未来の様々な見聞した断片を報告することから始めていきたい。
〈市電の趣〉

写真1:市電のある1920年代のボローニャ。
現在のボローニャ市内には路面電車は走っていない。写真1はマッジョ−レ広場のネプチューン像を背景に走行している1920年代の路面電車である。街の至るところ100年、200年単位で数えられる、歴史的建造物とでもいえるものが数多く存在する。一方では時代をさかのぼった当時の写真が額縁にいれられ、部屋の中で掲示されているのを散見することができる。
ある資料では、ボローニャの交通機関に関する年表を次のように記している(注1)。
1880〜1963年、最初に供用開始された馬車の牽引による路線網
1924年〜 市内路面電車開通
1958年〜 バスおよびトロリーバス運用開始
1963年〜 ボローニャにおける最新のバス路線の実現、路面電車等の撤去
つまり写真は初期の市内路面電車であり、第二次大戦後20年近く経て、最新のバス路線の実現と引き換えに撤去されるに至ったものである。そして現在は写真2のバスが運行されている。なお今後の交通機関のあり方として、新たな路面電車の復活が議論されるに至っていると聞く。その内容は旧来の復活ではない。しかし実現の程は、今は定かではない。

写真2:現在運行されているバス。
〈内部改装中の商店〉

写真3:内部改装中の商店。
日本と同じように、ボローニャでも、7月も中旬を過ぎると、バカンスにつき閉店、改修につき閉店などの張り紙が目につきだす。1軒、1軒と、日に日に商店の改装工事の数が増えていく。この夏の期間を利用した内部改装とでもいえる模様替え、つまりバカンス後の秋へ向けての準備が進行しているのである(写真3)。
先日は、メイン道路であるインディペンデンツァ通りでも大型のクレーン車がドンと据付けられ、何やら始まったようであった。片側通行となっていたが、何時ものことと察してか、ことは順調に運んでいたようである。
〈保存的開発〉
市街地の保存的開発については、日本でもすでにいろんな方々が報告されている(注2)。
ここでは、3人のそのさわりと思われるところを、まず記してみよう。
例えば三上禮次氏は、1988年のボローニャ市へのヒヤリングをもとに、「単なる物の保存ではなくてむしろ人の、社会の再生保存、そしてそのような内容の物的表現としての建物、街路の再生保存」を紹介している。
宗田好史氏は、都市再生を目指す戦略的再開発について、「歴史的都心部は、…単に建築形態学的に都心の歴史性が保存されるのではなく、都心の社会経済的な役割が継承され、都市の中での都心の主体的な地位が認められることで、歴史的都心部がその社会・経済的活力とともに、総合的に守られる」という今日の到達点を論じている。
さらには、佐々木雅幸氏は、都心部への創造的な文化空間創出がめざされた「ヨーロッパ文化都市・ボローニャ2000」の取組みの中の一例を次のように紹介している。「マッジョ−レ広場に面し、市庁舎に隣接する旧株式取引所は保存修復工事により、コンピュータ・ネットワークにリンクされた900以上の座席を持つ、イタリア最大の図書館として生まれ変わり、屋内ロビーにはさらに400の座席をもうけ、マルチメディア設備も利用できるように工事が進行中である」(その4で紹介した図書館写真参照)。
ボローニャ市図書館はすでに工事が完了し、市民への利用に供せられている。筆者もボローニャ到着後、利用者カードを発行していただいたところである。こうした保存的開発への努力には、積み重ねられた歴史に、限りない再生の努力を見ることができる。

写真4:通路としても利用できる再生された空間。
そこには学ぶべき成熟型都市の明日をみる思いがする。写真4は、外観は全く従来のままであるが、その内部は通路としても利用できる再生された空間であり、その片側、あるいは両側には様々な商店が並んでいる。
〈ボローニャの永続的な進歩発展を〉

写真5:ボローニャ再生計画を展示するパビリオン入口。
ボローニャの歴史的市街区の中心、マッジョーレ広場の一角には、時期を限ったボローニャ再生計画を展示するパビリオンの入口が目に入る(写真5)。階段を降り地下に入ると、ボローニャ大都市圏計画に位置づけた、再生計画の最初の説明書きが目に入る(写真6)。
限界と快別する行動、理念、価値/ボローニャ貯蓄銀行財団は、以前から街や地域、そこに住む人々のよりどころとなる考えを形成するために力を尽くしてきた。企業体の設立、公的利益のための民間の参加、自発的活動、そしてそれらを支持するあなたの行動は、ボローニャにおける共同体の進歩、歴史的・文化的・生産的なアイデンティティの進歩発展過程を補完する重要な構成部分である。
ここには限界と快別し、新しいボローニャを創り出していこうとする行動計画、理念、基軸となる価値は何なのか、を提示するボローニャ貯蓄銀行財団の決意を表しているものと考えることができよう。
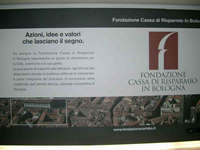
写真6:ボローニャ再生計画。
配布されるボローニャ市の資料には、この展示は今日と明日の計画をマルチメディアによってその過程を紹介するものであり、永続的な進歩発展を示したものであると記されている(注3)。以下多くのパネル・ビデオを使って、計画を練り上げていくための市民への啓蒙活動が行われている。中身の紹介については別の機会に譲ろう。
(注1)Piazza Maggioreの地下、-eBO-ESPOSIZIONE BOLOGNA展示の一部。2003年7月。
(注2)「都市計画と住民参加―ボローニャの試み―」1991年、三上禮次著、自治体研究社、p.56。 「にぎわいを呼ぶイタリアのまちづくり 歴史的景観の再生と商業政策」宗田好史、学芸出版社、p.66。 「創造都市への挑戦 産業と文化の息づく街へ」2001年、佐々木雅幸、岩波書店、p.78。
(注3)「-eBO-ESPOSIZIONE BOLOGNA」2003年, Comune di Bologna p.1。
|