 |
 |
同じ編者によるこのシリーズの紹介は、「戦国編」「江戸編(上)」に続いて3度目である。本巻も8人の作家による珠玉の短篇小説を集めたものだ。
世に知られる大奥女中絵島(えじま)と歌舞伎役者生島(いくしま)の禁断の恋を、権力者たちの派閥争いに押しつぶされてしまう犠牲者として描いた平岩弓枝『絵島の恋<絵島・生島>』、加賀騒動の中心人物として歴史的にさまざまな悪評をたてられてしまった男に、美女との艶聞を挿入することで手向けする戸部新三郎『影は窈窕(ようちょう)<大槻伝蔵>』、江戸城内七人切り刃傷事件を宮仕えの不合理として捉えながらユーモラスな時代劇として描いた小松重男『鰈(かれい)の縁側<松平外記>』なども傑作だが、なんといっても出色は古川薫『吉田松陰の恋』だろう。
安政元年の暮れ、異国の軍艦に潜入して密航を企てて失敗した吉田松陰は捕えられ野山獄(のやまごく)に投獄された。このとき同じ野山獄に囚われていた高須久子との間に淡い恋があったのではないかと、現存する相聞歌から推測した作者が、女囚の手記という形式で筆を執ったのがこの作品だ。
本編では松陰という人物が実に魅力的に描かれている。
一見はにかみやの青年だが、論じはじめるや声は高揚し顔面は紅潮し、口角泡をとばして聞くものを引き付ける。狂人と見紛うばかりに興奮するときもあるが、平穏に戻れば礼儀正しい温厚な学者だ。
獄舎は通路に向かい合って南北に二棟が軒を連ねていた。満室のときは12人、女性は一人だ。獄内での松陰塾は盛況で、通路にまで聴衆がはみ出していた。獄牢やいがみあっていた少しばかり学のある者たちも、知らぬまに松陰の感化を受けた。獄内の人たちは知識を広める機会が与えられただけでなく、句会もはじまったことで、交流・親睦や文化活動の花も開いた。
武家の娘とはいえ、政治や社会情勢に疎かった久子も、話の中身はともかく、松陰の内面にほとばしる情熱とやさしい人柄に惹かれていく。二度と外の世界に戻ることはあるまいと、無気力になりかけていた生活に一条の光が射し込んだ。
ここに入れられている人たちの罪はさまざまだが、久子は姦淫の罪であった。夫に先立たれた後、出入りの三味線ひきの男を深夜まで家に引き止めていたということが問われた。婚家を離縁された娘を実直な父は、「牢で姦婦でなかった証をたてよ」と男ばかりの獄舎に追いやった。その父は亡くなり、後を継いだ兄は一生涯ここに閉じ込めておくつもりらしいと松陰に語る。
当時、入獄期間が身内の受け入れの姿勢によって左右されていたというのは驚きだ。家が厄介払いしたい人を公が受け入れるという歪んだ福祉の制度であったともいえるが、やはり、個の尊重よりも社会や組織を安全に維持することが優先されていたということだろう。
肉親に見放され、生きる望みを絶たれそうになった女囚が、世界を見据える力と将来への夢を語る異性を愛しはじめた充実感はいかほどだったろう。また、国を憂えながら行動する知識人が、獄中に喘ぐ薄幸の女性の真心に触れた経験はなにものにも代え難かったろうと思う。
「清らかな夏木のかげにやすらへど人ぞいふらん花に迷ふと 松陰」。 しかし、松陰は一度は獄舎を去る。「鴫(しぎ)立ってあと淋しさの夜明けかな 高須久子」「子義(しぎ)」は松陰のもうひとつの号であった。
その後は、再び以前の暗い生活に戻ったような獄舎であったが、3年後、今度は「老中間部詮勝(まなべあきかつ)を大砲でぶっとばそう」という大言壮語が罪に問われて、松陰は二度目の下獄となり野山獄に帰ってきた。
しかし、再会を喜べたのは、死罪を待つまでのわずか5ヶ月間のことであった。最後の別れが近づいたことを知って、久子は松陰の室の暗がりに忍び込み、餞別に手布巾を差し出して「いつまでもお慕い申しております」と言った。
翌日、松陰から一枚の紙片を受け取る。そこには「箱根山越すとき汗の出でやせん君を思ひてふき清めてん 松陰」の一首が記されていた。松陰は最後の夜を実家で過ごしたので、久子の期待はかなわなかった。
別れの当日、錠前付きの駕籠に乗る直前に松陰から手渡された封書を、部屋に帰って開けてみると「一声をいかで忘れんほととぎす 松陰」と書かれてあった。 |
|
 |
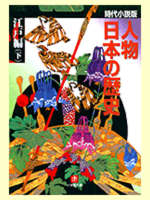 |
 |
『人物日本の歴史 江戸編(下)』
縄田一男 編著
小学館文庫
発行 2004年7月
本体価格 600円+税
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|