 |
 |
私の過ごした男子高校での人気投票でも、吉永小百合がやはり第一位を占めていたと記憶している。40年ほど前の話である。すでにサユリストという言葉が流行りはじめていた。
本書巻頭の幾葉かの写真を見るだけでも、昭和30年代後半が蘇える。高度経済成長前の時代、「戦後」が巷のあちこちに残り、それぞれが生きることに一生懸命で、それでもどこかに希望を抱いていたような時代はちょうど私の中高時代であった(中学入学が1960年)。
吉永小百合の映画デビューは1959年3月の『朝を呼ぶ口笛』で、15歳であった。それから、一躍人気スターとなった1962年4月『キューポラのある街』までの28本の作品を追った映画論だ。著者は、そうした映画を見直すことで、女優・吉永小百合を再発見できるのではないかという期待を持ったのだった。
私が興味を持ったのは、“小百合像”が作られるまでの映画会社の苦心と努力の跡とともに当時の作品の筋立てで、どこかで見たような通俗的なものであっても、味わい方によって別の奥深い内容を提示していたりすることの発見であった。
当時の作品はどれもみんな、前向きな姿勢を示す感じのいい映画ばかりだったように思える。
『朝を呼ぶ口笛』は、貧しい家の新聞配達の少年・稔と、その兄貴分で新聞店に住み込んで夜間の大学で勉強している須藤さん、それに集団就職で東京に出て来ているバス・ガール・静子をめぐる話だ。
稔は高校に行くためにいくらかの貯金をしていたが、母親が倒れたことで、入院・手術の治療費が必要になる。一度は高校進学をあきらめた稔だが、新聞店の仲間たちのカンパで初心を貫くことが可能になった。
須藤さんは一流企業の就職試験に失敗する。夜間の大学ということが不合格の理由のようだ。しかし、地方の鉱山への就職がきまり、思いを寄せていた静子も後を追って行く。
けなげな少年たちの生活の苦労の話や、青年たちの恋愛の話が主な筋立てだ。
吉永小百合は、稔の配達先の中流家庭の娘として登場する。新聞が紛失するのを突き止めようとして稔と知り合う。稔の自転車が壊れたとき乗っていた自転車を貸し与えたりする役だ。
しかし、ここで著者は言う。
「日々を精いっぱいにこなして生きている庶民を、どの人もほどの良いリアリティのなかに提供することに、すんなりと成功していることがよくわかる。…そこからやや外れるのが刈谷美和子(吉永小百合の役)だ。セーラー服のときには、他の人たちとおなじリアリティのなかにいる人なのだが、私服の場面になると、どこかに架空感の漂う人となる」と。
小林旭や赤木圭一郎、和田浩治などが主演した“流れ者”映画でも、だれもが人間関係の網の目にからめ取られているときに、吉永小百合だけはそれが何もないから浮いて見えてしまうことも多いという。
このころの小百合は、主人公の妹とか娘といった脇役が多かったが、すでに明るい未来をまっすぐに見つめる少女という役どころは決まりつつあった。ただ、それが生活に余裕のある家庭の娘である場合はいつも、納まりが悪かったようだ。
「正しい方向に向けたまっすぐな熱意や誠意、あるいは希望などを体現する、若くてきれいで、清潔な雰囲気そのもののような存在としての女優」は、貧しい庶民の娘である『キューポラのある街』のジュンを演じることで確固とした足場を築いた。
『朝を呼ぶ口笛』で、昼間の高校への進学をあきらめ夜間の高校に通う選択をした新聞配達の少年・稔に「ガンバレ」と紙に書いて手渡した少女は、『キューポラのある街』では、みずからが昼間の高校への進学をあきらめ、職に就きながら夜間の高校に通う少女となって現われたのだ。
実は私は、ここでとりあげられた28の作品のどれひとつとしてリアルタイムには観ていない。
学校で映画館通いが禁止されていたということもあるだろうが、さほど映画に魅力を感じなかったのか、もう少し年長の人たちが観たのか、学生ではなく労働者が観たのか、そもそも、まだ駆け出しだった頃の吉永小百合に注目していなかったからだろうか。 |
|
 |
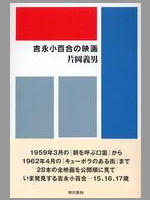 |
 |
『吉永小百合の映画』
片岡義男 著
東京書籍
発行 2004年9月
本体価格 1600円+税
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 筆者紹介 |
 |
若田 泰
医師。京都民医連中央病院で病理を担当。近畿高等看護専門学校校長も務める。その書評は、関心領域の広さと本を読まなくてもその本の内容がよく分かると評判を取る。医師、医療の社会的責任についての発言も活発。飲めば飲むほど飲めるという酒豪でもある。 |
|
|
 |
|
|
|